みなさん、こんにちは♪
COCOHEプロデューサーの内田です。
昨日、COCOHEでいつも素敵な歌を歌ってくれている柳内ゆうすけお兄さんが主演を務める舞台を観てきました。
何をネタバレとするかによりますが、ネタバレとおもってないけどネタバレになることがあるかもね。という補足を一応いれておきます。
「ワーニャおじさん」という演目でそのワーニャおじさん(タイトルロール)を務めたのがゆうすけお兄さんでした。
COCOHEで見せてくれるお兄さんとは全く別の顔でした。
改めて、すごい人にCOCOHEに出演してもらっているんだなと感じまして、こんなに素晴らしい才能があるお兄さんに一緒に舞台に立ってもらえてありがたいなぁとおもった次第です。これからもなにも公演がない時はよろしくおねがいします。
さて、その「ワーニャおじさん」楽しいお話ではありません。(今回の演出では随所にクスリと笑える要素はありますが・・・)
自分の理想と現実と向きああって、葛藤して、苦しんで、苦しんで、それでも生きていく。
みたいなお話です。
なにそれ、辛っ!!!!
そこに複雑な人間関係(人に対する想い)が絡み合ってくるんですけど、人間関係って終わりかけのジェンガみたいに絶妙なバランスで成り立っていることがある。
一歩動くと壊れるような。そんなバランスになってしまう時ってあるじゃないですか。(え?ないの?)
気持ち的には前に一歩出したいのに、出したら壊れるな。でも、もう後ろにも引けないな。みたいな時ありますでしょう?
結局動かさないでそのままを維持する道を選んだりするわけよね。私も臆病なのでそんな選択をすることはあります。バランス大事だしね。笑
人間誰しも生きていく中で多かれ少なかれ理想と現実というものに向き合う瞬間って誰でもやってくるのかなと思います。
理想通りに生きている人なんて少ないと思います。
その中でどう、折り合いをつけていくか、折り合いの付け方はテクニック的な部分もあって、うまいこと折り合いつけて行くほうが幸せなんだろうなと私は考えています。
どうにもならない思いが自分にだってないわけじゃないし、これまでに体験してきたことではあります。でも苦しいことばかりに目を向けて生きるのはそれはそれで私は怠慢なんじゃないかと思うわけです。笑
そもそも不幸でい続けることなんてできなくない?どんなに窮屈な満員電車も走り出すと多少のゆとりは生まれるように、どんな不幸だと感じていても、だんだんその不幸に慣れてくる。不幸であると感じ続けられるとしたらちょっとした才能だと思うのです。
ワーニャおじさんは不幸であることに気づいてすべてのアンテナを切ってしまうのだけど、とはいえワーニャおじさんのまわりには幸せいっぱいあるのになーと私からは見えるのです。それを受け取る余裕がないのか、受け取りたくないのか。あるいは不幸で在ることで心を支えているのかもしれません。そういう意味で頑固な人です。笑
で、これは終演後に一緒に見に行ったゆうこお姉さんやさおりお姉さんともお話したことですが、つまりこれは〈ロシアっぽさ〉なんじゃないか。という話になりました。
このお話を書いたのはロシアの作家チェーホフで、やっぱりロシアの気候って物事をネガティブに捉えさせてしまう何かがあるのかもね。という結論だったのです。日本に暮らす私たちには想像し得ない心境っていうものがあるのだろうなと・・・。
そんな事を感じながら、そんな私の中に心地よい違和感と後味をのこしたワーニャおじさんなのでした。
自分とまったく異なる行動や考えをする人間を客観的に観察する。それが演劇の面白さの一つだなと思いますし、それを描くのが俳優さんの腕の見せどころだと感じます。
そういう意味でやっぱりゆうすけお兄さん素晴らしかったです。
そんなワーニャおじさんの感想からのそれと対象的な春の音楽絵本のプログラムから春の音楽絵本に関しての解説引用です。
冬の音楽絵本で〈家〉に諭されて、少女は四季を巡る旅に出ます。そしてこの春の音楽絵本は少女が最初に旅をした時のお話です。
少女は冬の音楽絵本で「心から幸せを感じて欲しい」という家の願いから旅に出ますが、少女にとって「幸せ」は何か特別なものという漠然としたイメージしかありませんでした。
ですから、森の奥にある桜の木に願い事をすると幸せになると人から言われるままに、漠然と幸せを探しに森へやってきます。
「自分にとっての幸せがなんなのか?」という問に対する答えが漠然としている人は少なくないはずです。
そんな時に厳しい自然の中で生きているクマの子と出会い自然の中で彼女は様々な事を感じて、自分なりの答えに近づいていきます。
この物語の中で少女は大人、クマの子は子どもを象徴しています。この物語の中で少女に寄り添い、教える立場にいるのはクマの子の方なので逆をイメージされる方も多いかもしれませんが、子供と一緒に過ごしていると情けないことに子供から教えられることがとても多いので、そのようなイメージで物語を書きました。
物語の最後に少女とクマの子は小さな種を見つけます。
この物語で伝えたかったのは大きな幸せを求めるな!という乱暴な話ではなく、今この瞬間を全力で生きること。そして今、手の中にある小さな幸せを感じてそれを紡ぎながら、自分の手、そして愛する人の力も借りて大切に育てていった先に本当に自分にとって大きな幸せが待っているんじゃないのかな?というそんな投げかけです。
このステージを見終えた時に皆さんの隣、あるいは膝の上にいる子を改めて優しく優しく抱きしめたくなるようなそんなお話にしたいなと思いながら書き上げました。
旅の始まりとなる春では少女は「小さな命」に目を向けます。そして、夏は「等身大の命」。秋は「壮大な命の巡り」というように少女の学びが彼女の世界を広げていくそんなイメージでシリーズを作っております。
何が幸せか漠然と見えぬまま幸せに手を伸ばす人もいれば、はっきりと幸せが目の前にあっても掴めない人もいる。
人間ってややこしいですな。笑
「辛」と「幸」って漢字にているでしょう?もともと刑罰や苦しみを象徴するところから出発していんですって。
辛いことのすぐ近くにちゃんと幸せはあるのであす。
ということで、結論。
ワーニャおじさんみたいな人がもし世の中にいるならば、あたたかい春の風がその人の心に吹きますようにと願いを込めて。






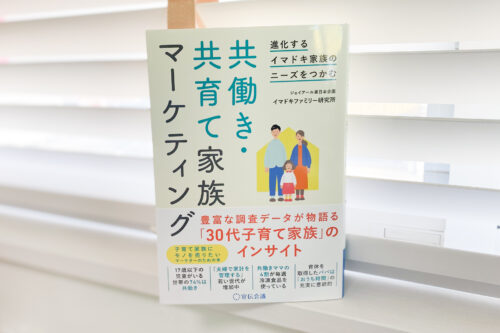







-1.png)